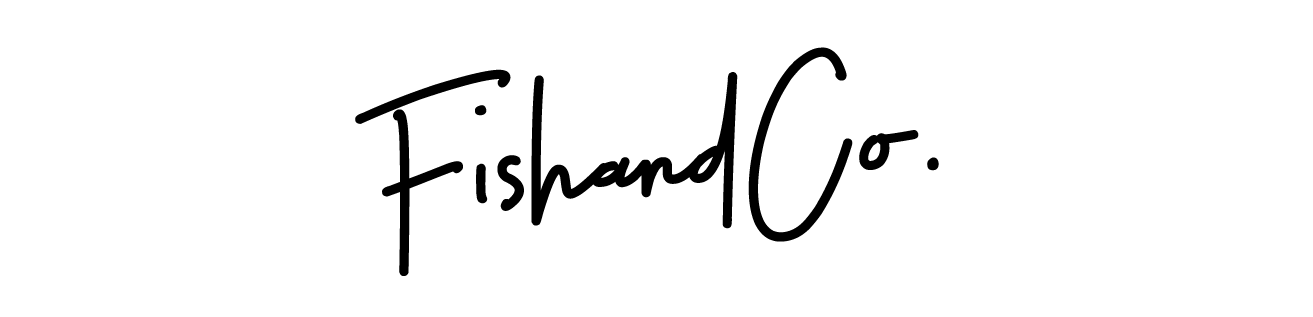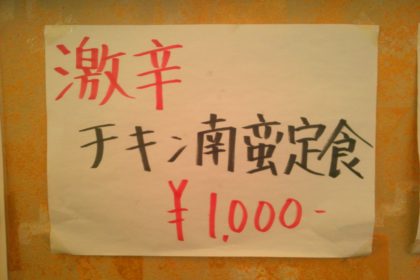松浦弥太郎著「考え方のコツ」を読んで目からウロコ
去年あたりから『暮らしの手帖』を愛読するようなりました。
あれってめちゃくちゃ面白いんですね!知らなかったー。
お母さんたちが読む雑誌とばかり思ってたんですけど、今ではバックナンバー探しにブックオフ通いの毎日です。
そしてその流れで元編集長である松浦弥太郎さんの本を手に取るように。
今回一気に読んでしまったのが『考え方のコツ』という一冊。
最近ワタシの中でモヤーっとしていた「考える」ということに対するヒントが見えてきた気がします。
早くも「マイベストオブ今年読んだ本」にノミネートされました。
考えることは辛い、でも楽しい
考えるということは、難しい。放棄したくなる。だって、誰だってめんどくさいことはやりたくないですしね。
でも考えるということをしなくなると、ただがむしゃらに頑張るだけで、目的地も、本来の目的自体も見失ってしまいそうです。
せっかく仕事を頑張っても結果が出ない。
せっかく野球の練習をがんばっても上手にならない。
商品を売りたくて頑張ってるのに、全然売れない。
そんなときは一度立ち止まって、じっくり考えてみることが必要なんじゃないかと思います。
そもそも?
そもそも自分がいま担当している仕事自体が、本当にやるべき価値があることなんだろうか?
もっと違うアプローチでプロジェクトを進めたほうがホントはいいんじゃない?
そもそも、野球がむいてないんじゃない?他のスポーツのほうが上手にできるかも?
(それでも野球がやりたかったら今よりもっとよい練習法がないか考えてみる)
もしかしたら自分が売ってる商品(もしくは売りたい商品)がほんとはお客さんが求めているものじゃないんではないか?
そもそもなんでその商品を売りたいの?
とにかく考えてみる。
そして考えることを途中で諦めない。
実際、松浦さんはA3くらいの白い用紙とペンを用意して1日2回、各1時間、ひたすら考え抜くそうです。
全然アイデアが出てこないこともあるし、大変なんだけど。
「なに、なぜ、なんだろう」と考え抜く。これが大事だとのこと。
そうすれば自分なりのオリジナルの考え方にたどり着ける、と。
自分も考える事をかなり意識してたつもりなんですけど、まだまだ全然足りないな、と思い知りました。
「考え抜くこと」「諦めないこと」。
考えることの先に見えてくる、本当に大切にしたい考え方がなんとなく分かった!
考えるということはもちろん何かを変えたい、良くしたいという何かしらの目的のもと行うと思います。
でも、何をもってその「目的」を設定するのか。
自分が幸せになりたいから?これをやると売上が上がりそうだから?お客さんがたくさん来てくれるから?
ここの部分が自分の中で今まで曖昧だった気がするんですが、この1文で視界が開けました。
~自分の思いつく限りの想像力を働かせると、自分のアイデアが正しいか正しくないかを超えた、「その先の人が幸せになるかならないか」という答えが見えてくる気がします~
目からウロコ。
やっぱりたどり着くところはここかー、という感じで。
自分がいまこの行動をしたら、その先にいる人たちにどんな良い事があるのか?
どんな些細なことでも良いと思います。
いま自分が目の前に売られている牛乳を一本買うことで、だれにどんな恩恵が行き渡るんだろう?
牛は嬉しいかな?酪農家の人たちは嬉しいかな?牛乳を運ぶ仕事をしてる人は嬉しいかな?牛乳を取り扱ってるお店の人は嬉しいかな?とか。
可能な限りの想像力を働かせて、喜んでくれる人が多そうなら間違いなく買うという選択をする。
仕事のプロジェクトでもそこが大切かもしれませんね。
というわけで、こちらの一冊、なんの迷いもなく本棚行き決定です。
松浦弥太郎さんの本、まだまだたくさんあります。
同じカテゴリの記事
「革命のファンファーレ」を読んでサカナ釣りの楽しみ方を考察する
「THE POWER OF LESS-減らす技術」を読んで断捨離生活に弾みをつける
夏の読書にオススメ!ジュール・ヴェルヌ著「海底二万海里」がおもしろい!